このような生きづらさを抱えてませんか?
✔人と接すると疲れる
✔争い事が苦手
✔理不尽な相手に言い返せない
✔自分は悪くないのに、悪い様な気がしてしまう
✔人になめられる
✔学校や会社でいじめられる
✔嫌われたくなくて、言いなりになってしまう
✔頼まれたら断れない
✔良い様に使われてしまう
✔不機嫌な人の機嫌を取ろうとしてしまう
3つ以上当てはまる方は、やさしい性格のせいで生きづらい人なのかも知れません。
ご挨拶

はじめまして。
愛知県豊田市で、やさしい人が笑顔になる整体院 無為楽堂の院長 中村俊文(ナカムラ トシフミ)です。
人にやさしくするって、良い事だと思いし、気持ちいいですよね。
私もそうです。
しかし他方で、やさしさは弱さや搾取の対象になりやすく、生きていく上で損をしがちではないでしょうか?
私の整体院に来る自律神経を病む方の多くが、やさしい方でした。
生きづらさを抱えてました。
それを見て、やさしい人達をどうにか生きやすくなって欲しいと考えて、このサイトを立ち上げました。
なぜ、やさしい人が生きづらいのか?

やさしさの価値が下がっている
人が死ににくくなった
本来やさしさとは、一人では弱い存在である人間が、生き残るために助け合う感情だと思います。
野生の世界では、人間は簡単に死んでしまう可能性がありますからね。
人類社会の都市化が進み、安全になり、物質的に豊かで、社会保障などが充実して、人は簡単には死ななくなりました。
その結果やさしさの必要性が少なくなりました。
逆に価値が上がってきたのが、やさしさとの真逆の「競争」です。
学校や会社では競争させられ、プライベートやSNSではマウント合戦。
競争で勝つことこそ、正義な世の中です。
競争はしたくない

人にやさしくしたい人にとって、やさしくすることは信念であり、本能だと思います。
これを曲げる事は、自分じゃなくなるくらいの感覚だと思います。
それは自分にやさしくない。
競争も出来なくはないけど、凄い本気にはなれない。
負けた側に同情してしまう。
競争はほどほどにしたいのです。
競争の対象にはされる
こっちは競争したくなくても、他人は競争を挑んで来ます。
やさしい人は競争を望まないので、競争したいというか、勝ちたい人にとっては、恰好の獲物です。
やさしい人は攻撃されても、反撃はしません。
やさしくしたいわけですから。
そして傷つく。
競争が推奨される社会では、やさしい人は生きづらいのです。
なぜ、当院の施術で生きやすくなる?

①院長 中村が同じやさしい人だから
以前勤めてた会社で「中村さんってやさしいんですね」と言われて、ハッと気が付きました。
私はやさしい人なんだと。
同じやさしい人同士は、共感を生みやすいですね。
共感は、癒しの入り口です。
②自律神経が整うから
自律神経専門整体院の本領発揮です。
自律神経が整うと、心身ともに余裕が生まれます。
余裕があると、落ち着いて良い判断が出来ます。
やさしい人の生きづらさを軽減出来ます。
③考え方が変わる
考え方が変わると、早く楽になる事が多いです。
考え方は、知っているか?知らないか?が大きいです。
私がお伝えできる事は、すべてお伝えします。
施術について
1回あたり30分はお話で、30分は施術です。(長くなる事もあります)
大体、10回来院で効果を実感できる事が多いです。(早い方なら5~6回)
何か症状をお持ちなら週一回、なければ2週に一回程度からのスタートをお勧めします。(強制はしません)
料金は一回5000円(初回は6000円)です。
来院されている方に起こる変化
来院されている方に起こる変化は、人それぞれ違いがありますので、保証は出来ません。
代表的な変化をリストアップしました。
・笑う事が多くなる
・パートナーができる
・仕事をし始める
・良い職場に行くことができる
・苦手な人がいなくなる
・体調が良くなる
・穏やかに日々が過ごせる
・長年の問題にケリがつく
・トラウマが癒される
・運が良くなる
これらの変化が起こる理由はちゃんとあります。
体験してのお楽しみ。
終わりに
成功って何だろう?
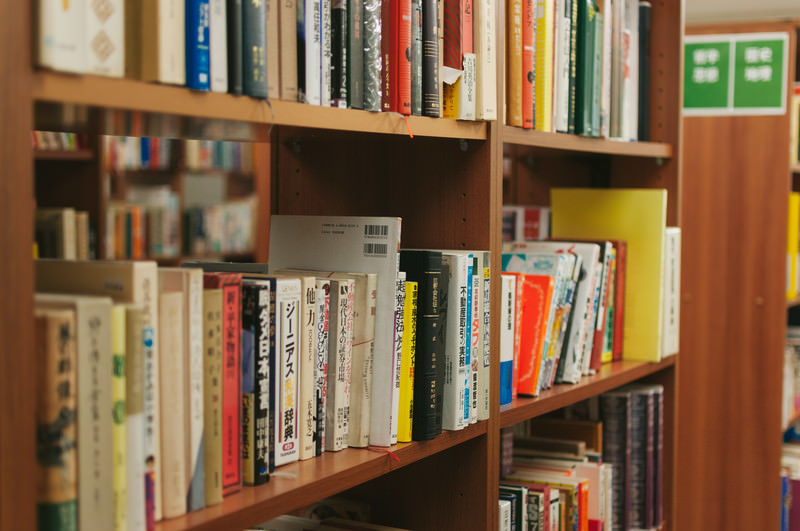
本のタイトルなどで、「成功」とか「成功者」っていう言葉をよく見かけます。
お金持ちだったり、事業や投資で大儲けしたり、大企業の社長の話だったり。
しかし、最近は少しづつ変わって来てる様な気がします。
これからの「成功」とか「成功者」の定義は、「憧れられてる人」じゃないかと私は思います。
イメージとしては、ユーチューバーとかSNSのインフルエンサーが思い浮かびますが、すぐ消える人もいるので、長く支持されている事も条件でしょう。
どんな人が「憧れられている人」か?

私の意見では、「社会の簡単に解決出来ない問題に取り組んでいる人」が結果的に「憧れられている人」になるのでは、と思います。
私はそういう人のユーチューブや記事をよく見るし、バズっている様にも思えます。
自分にはとても出来ない難しい事だから、変わりに取り組んでくれるその人を応援する。
そうやって応援されている人が、だんだん「憧れられている人」となり、後に「成功者」と呼ばれるのではないでしょうか。
だから、「成功」とは「社会の簡単に解決できない問題に取り組む事」そのものだと思います。
解決できるできないは別で。
私も「成功者」になることが目的ではないですが、「社会の簡単に解決できない問題」として「やさしい人が社会で生き易くなる事」に真摯に取り組んでいこうと考え取り組んでいます。
